それは、風のように駆け抜け、稲妻のように儚く散った天才だった。
サイレンススズカ。今なお競馬ファンの胸に熱く刻まれている。
その走りを見た者は言う。「生涯であの馬を超える存在には出会っていない」と。
彼が生まれたのは、北海道平取町・稲原牧場。1994年5月1日、父サンデーサイレンス、母ワキアの間に生まれた小さな栗毛の牡馬は、期待されぬ存在だった。父も母も青鹿毛と鹿毛。だが産まれた仔馬は鮮やかな栗毛。それは「走らない毛色」と言われていた。しかし、彼の身体には“ただならぬもの”が宿っていた。
幼少期から目立ったのはその集中力と闘志。そして、誰よりも走ることを愛した。育成中、深い雪に埋もれても平然と進み続ける彼の姿に、スタッフたちは驚嘆した。気性は激しく、馬房では何時間も左回りに回り続ける「旋回癖」を見せるほど。だが、それはただの癖ではなかった。彼にとって“走る”ことが、生きることだったのだ。
衝撃のデビュー、そして試練
1997年2月。京都競馬場でデビューしたサイレンススズカは、まさに衝撃を与えた。先頭で飛ばし、2着に7馬身差。騎乗した上村洋行騎手は「間違いなく大きなところを獲れる」と確信した。
だがその後、試練の連続が待っていた。弥生賞でのゲート事故、日本ダービーでの折り合い難。繊細すぎる気性と未成熟な精神。それでも彼の素質を信じる者たちは諦めなかった。
覚醒、そして“逃げ”という宿命
1997年暮れ、香港国際カップで武豊と新コンビを組むと、彼の運命が変わる。初めての“逃げ”という戦法。それは彼にとって「解き放たれた瞬間」だった。押さえ込まず、自由に走らせることで、サイレンススズカの真の姿が現れたのだ。
1998年――5歳となった彼は、無敵となった。
バレンタインS、中山記念、小倉大賞典、金鯱賞、宝塚記念、毎日王冠。立て続けに6連勝。しかも、いずれも後続を突き放す“逃げ切り勝ち”。時には10馬身以上の差をつけ、スタートからゴールまで一度も影を踏ませなかった。
特に毎日王冠でのエルコンドルパサー、グラスワンダーとの「伝説の三強対決」は、今も語り草だ。59キロの斤量を背負いながら、無敗の2頭を一切寄せつけず2馬身半差の圧勝。武豊の「楽勝でしたね、いやあ、強かったぁ」という言葉がすべてを物語る。
あの日、東京競馬場を埋め尽くした13万人が目撃したのは、間違いなく“異次元の存在”だった。
宿命の天皇賞、そして永遠へ
1998年11月1日、天皇賞(秋)。満を持して迎えた最大の目標。1枠1番、1.2倍の支持、最強のコンディション。レース前、武豊は言った。「オーバーペースで行きますよ。」
その宣言通り、サイレンススズカは1000mを57秒4で通過し、3コーナーでは2番手に10馬身差。しかし――その時は突然訪れた。
4コーナー手前で彼は失速し、競走を中止。左手根骨粉砕骨折。予後不良と診断され、その場で安楽死となった。
後に武豊は語った。
「あんなトップスピードで骨折して、倒れなかった馬なんて見たことがない。僕を守ってくれたのかなと思いました。せめて、あと数百メートル…走らせてやりたかった。」
ファンの中にはあの天皇賞は、今も“奇跡と悲劇の交差点”として語り継がれる。
風は、今も走り続ける
彼が生きていたら――。きっとアメリカ遠征も、ジャパンカップも、夢ではなかった。サンデーサイレンスの後継として、種牡馬としても大きな期待を集めていた。
しかし、彼は走り抜けることを選んだ。
最後まで美しく、速く、孤高に。
墓標には、彼の蹄鉄とたてがみが納められている。そして、今もなお、北海道平取町には多くのファンが訪れる。
その姿に、橋田満調教師は静かに語った。
「サイレンススズカは、競馬が好きだったんだと思います。心から、走ることを愛していた。」
風のように駆け抜け、記憶に刻まれ、永遠に走り続ける――
サイレンススズカ。君は、永遠の疾風だ。
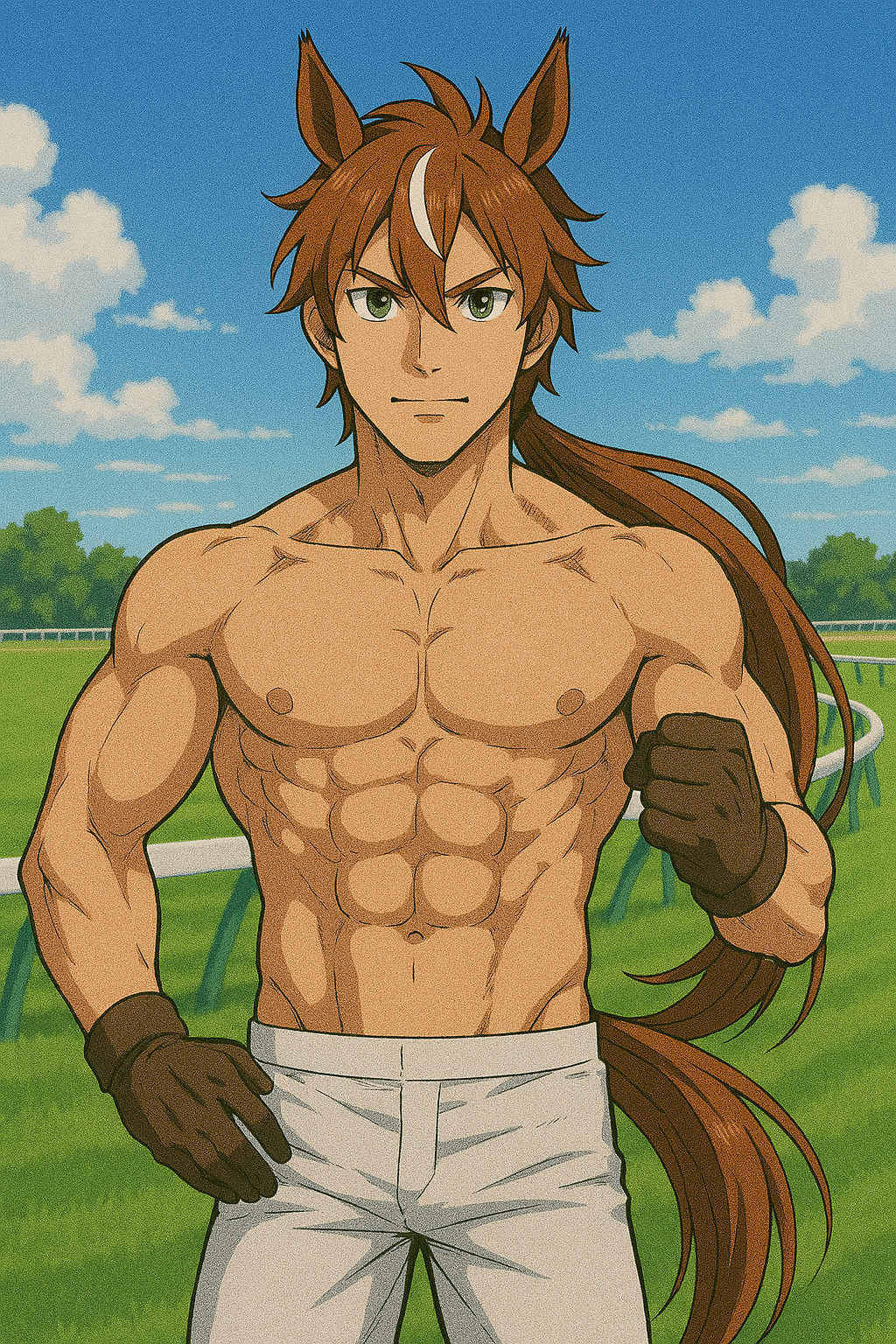
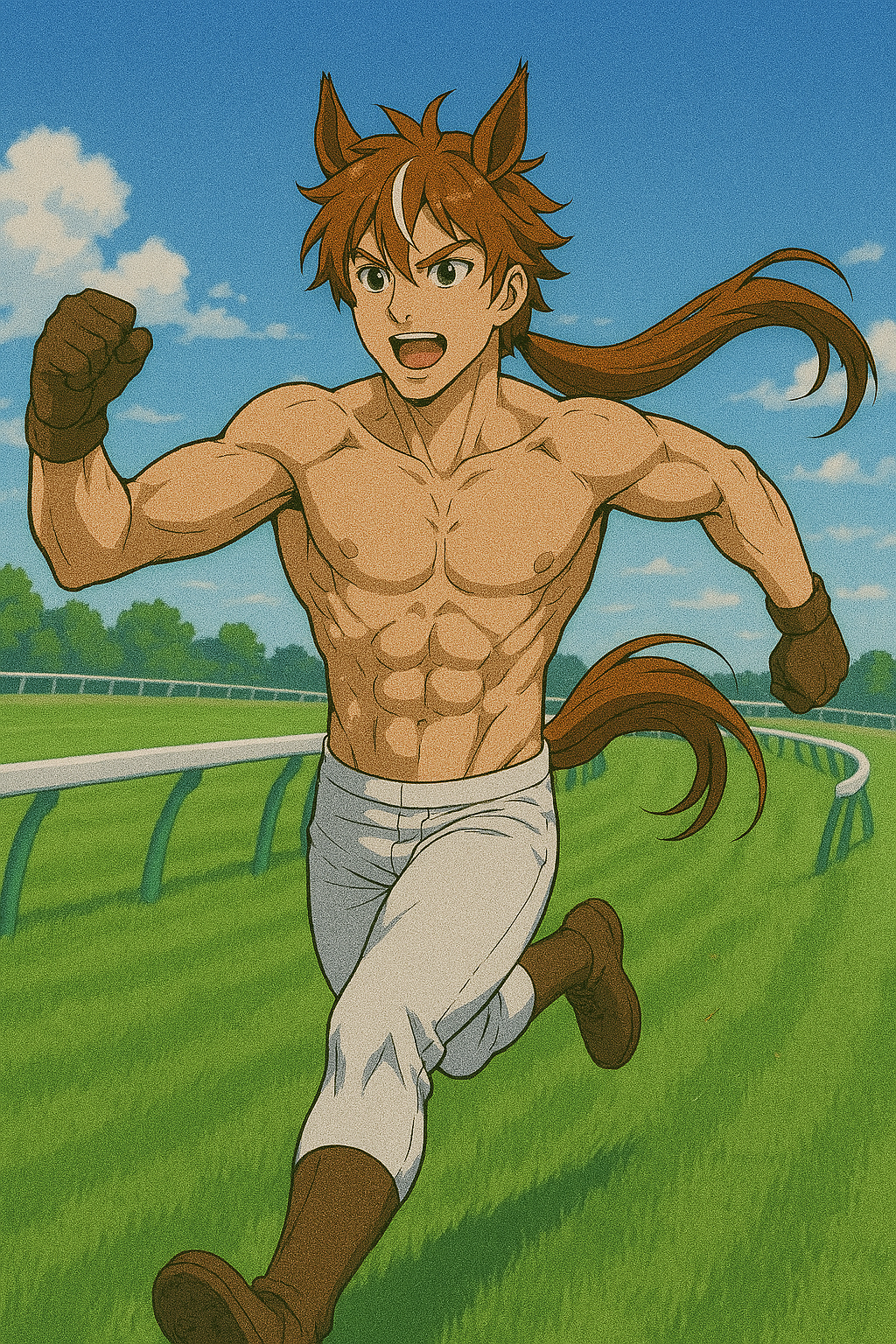
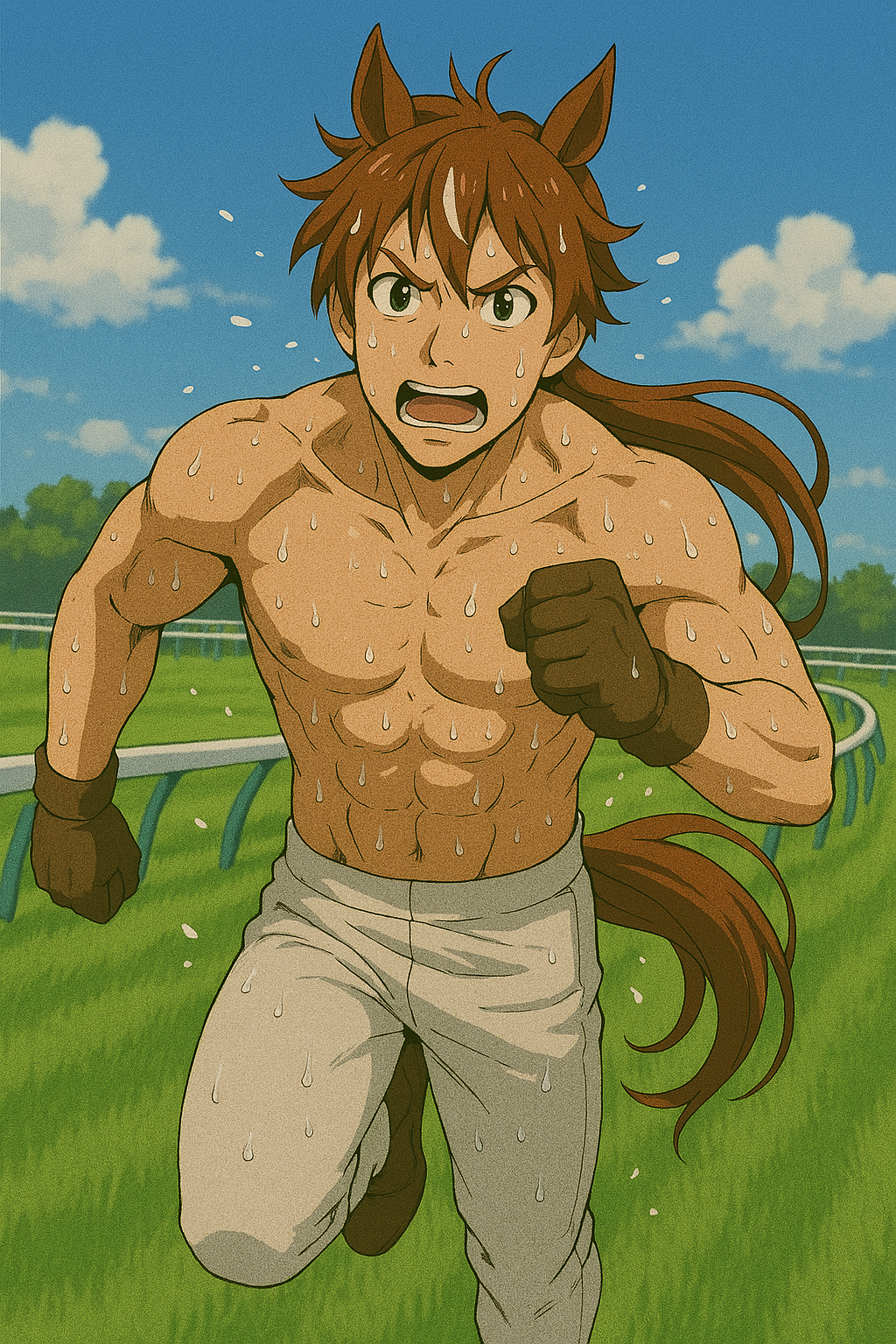

レビュー0